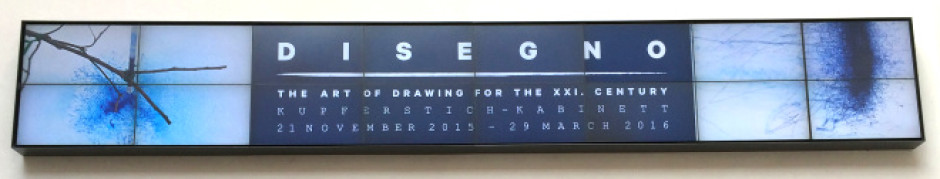リザボー通りを左へ曲ると、突き当たりでタクシーは止まった。
「ここよ...」とデビーが言った。
棟続きの奥から2番目。3段程の石段を上がり、ベルを押した。
たしか、ニュージャージーに住でいる友人のアパートも、リザボー通り だった。多分この通りの上には、ため池が有るはずだ。
そんな事をぼんやりと考えていると、ドアが開き、ロッドスチワートを 思わせる風貌の男が顔を見せた。
キッチンに案内され、紅茶をご馳走になった。
デビーは、明日の朝7時に迎えに来るよと言い残して、帰っていった。
ここでロッドスチワートに似た彼と、2週間暮らすことになった。
彼の名前は、ガイといった。ガイが、ひとしきり部屋を案内してくれた。
一階には居間があり、ソファーの上に大きなぬいぐるみがたくさん並ん でいた。
廊下の突き当りがキッチン。
右手のドアを出るとポーチがあり、奥まった庭は広かった。ドアには猫 が出入りする扉
が付いていた。近所の猫が遊びに来るということだった。
二階が、ガイの寝室とオフィス。バスルームがあり、階段には母親の若 い頃の写真が飾ってあった。
三階の屋根裏が僕の部屋だった。
そんなに広くはないが、ベッドに寝転ぶと大きな天窓から空が見 え、快適だった。タンスの引き出しを開けてみると、タオルがき れいに並んでいる。週に一度、掃除をしにきてもらっているとの ことだった。
彼の寝室以外は、どの扉も1cm 程開けてあった。それが、「入っ ていいよ」というサインだと分かるのに3日かかった。寝る時以 外は、僕の部屋の扉も1cm 開けておいた。
彼の仕事は一風変わっていた。ストーリーテラーといって、学校 や公共の場所、個人の家へ出向いて行って、お話をすると言うも のだった。僕は、説明されてもイメージがわかなかった。
デビーには、自炊してねと言われていたが、結局、ガイが毎日ご ちそうを作ってくれた。
あっと言う間に一週間が過ぎた。
土日を使って、バーミンガムから電車で3時間のロンドンへ行っ て、友人のダグに会った。
パブを梯子して、ひとしきり飲むと、ダグの友人の誕生パーティー に誘われたが、飲みすぎた僕は、ダグの部屋でくつろぐことにした。
ダグが出て行くと、入れ替わりにクリスティーナが入って来たの で聞いてみた。
「イギリス人てどう?」
歌手志望の彼女は、北欧から来てロンドンに住み着いているとの 事だった。
「私は、ここに慣れるのに2年かかったわ。褒められても真に受けてはだめよ」
「私なんてね、すっごく褒められたの。また行くよって言ったんだけど、来たためしはないんだから」
「だけどね、一旦親しくなると驚くほど気を使ってくれるの。そこ までいくのが大変なの。何度もテストされ、それを全てクリアー しないとそこまでいけないの」
「会話の中に、そのテストが隠されているのよ、わかる?」
彼女は延々と喋った。
バーミンガムへ戻ると、いつもどおり、早朝にデビーが迎えに来て、 近郊の学校へ出かけた。
今日は、上品な感じのボッドレイハイスクールだった。
教室へ入り、デビーが机に腰をかけて美術の変遷を簡単に説明し
た後、僕の仕事である学生とのワークショップが始まる。
ワークショップが終わると、学校の食堂で昼食をとってから、別 の学校へ移動する。これを毎日繰り返していた。
この日もワークショップを終えて自分の部屋へ戻り、靴を履いた まま、ベッドにごろんと仰向けになった。
天窓の青空を雲が横切るのをぼんやり眺めていると、突然大きな 音でモーツアルトが聞こえてきた。
階段を駆け下りると、ガイが上機嫌で料理を作っていた。
ステレオのボリュームはMAXまで上げられ、キッチンの窓と裏 庭につづくドアが開き放たれていた。
僕は、怪訝な顔で聞いてみた。
「こんなにボリューム上げて大丈夫?」
「今日は、特別の日なんだ、別れた妻の誕生日。この曲は、初めて のデートで行ったコンサートの曲だよ。」
「いつごろ別れたの」
「2年半前、今はあそこに住んでいる」
ガイが指さす方を見ると、キッチンの窓越しにバックヤードの庭があり、その 奥に、ここと同じような棟続きの建物が見えた。
「2階のあの窓だよ」
ガイは、うきうきしながら、特別料理を作り出した。猫よけの竹 串に囲まれた裏庭にハーブを取りに行くと、半開きのドアを、さ らに大きく開けて戻ってきた。
料理をしながら、窓から向かいを見つめる。
テーブルに付くと、ガイはワインを注ぎ、さあ食べようと笑顔で 僕を促した。
去年は、誰と食べたのだろうと思いながら聞いてみた。
「どうして出て行ったの」
ガイはワインを一口飲んだ。
「僕の仕事は、出歩く事がとても多いんだ。それが原因かな」
「彼女は、まだ再婚していないの?」
「一人で住んでいるよ」と、ガイは即答した。
食事が済むと、ステレオのスイッチを切り、セレモニーは終わった。
食器をディッシュウォッシャーに入れる間も、ガイは窓から目を離さなかった。 こんな特別の日に、僕とさしむかいでごちそうを食べる彼を、気の毒に思った。
ヒュウと風が吹き、庭の金鳳花が揺らめいた。
ガイが新しいワインの栓を抜いた。
小さく切り分けられた特別のチーズを彭ばりながら、ワインを飲 んだ。
彼女の事をもっと聞きたいと思ったが聞けなかった。別れた妻が なぜ、あのマンションを選んだのか知りたかった。
翌朝、助手席でリンゴをかじりながら、運転するデビーに昨夜の ことを話し始めると、「話さないで」と、さえぎられた。
ワークショップの仕事も終わり、最後に小さな展覧会とパーティー をしてくれた。
ディナーに招待する人を知らせてほしいと言われたが、知り合い がいないので、唯一知っているダグと、ハミッシュフルトンの住 所を告げた。
2人とも来ず、テーブルのネームプレートだけが残された。
デビーが、とっても気を使って「ハミッシュフルトンはテートで 個展中だから来られない」と言ってくれた。
帰国の前日に、ガイが友人のボブを呼んで、肉の詰め物をした特 別料理を二人で半日かけて作った。
僕は、小太りで陽気なボブとガイが、キッチンに並んで立ち、鼻 歌交じりに料理をしている後ろ姿を、眺めていた。
ひょっとしたら、彼女が出て行った原因は...と感じながらワイン の栓をぬくと、庭のポプラがそよいだ。
 2002,7
2002,7